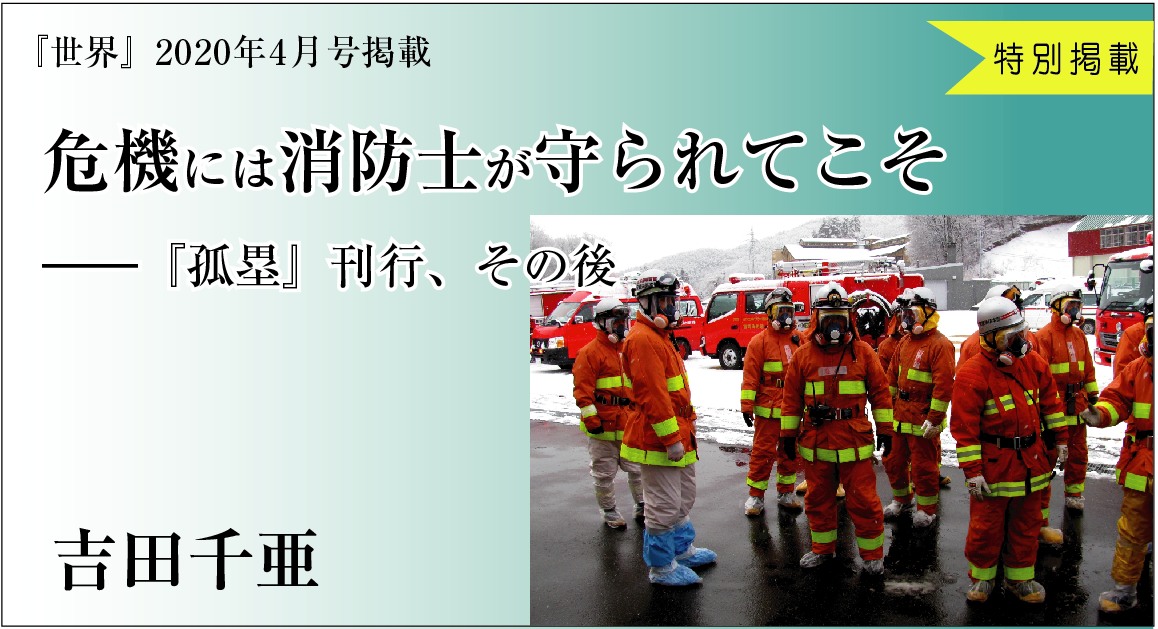〈特別公開〉危機には消防士が守られてこそ ――『孤塁』刊行、その後
※『世界』2020年4月号収録記事を、特別公開します。
繰り返される「失敗」――新型コロナウイルスと3・11
日に日に状況が悪化している新型コロナウイルスの報道は、3・11の再現ではないかと苦しい思いで見ている。
クルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス」の現場の様子はほとんど伝わらず、かろうじてSNSから伝わってくる断片的な情報は、例えば感染危険地帯と安全地帯のゾーニング(区画)の写真一つとっても(2月20日・橋本岳厚労副大臣撮影)、「本当にこういった有事に備えていたのだろうか」と愕然とする。本誌発売の3月初旬には、日本はまた違うステージにあるのだろう。
何より、陽性だった患者を搬送した救急隊員(2月15日・報道)の感染も確認されたことは、双葉郡の消防士たちのことを思い出さずにはいられなかった。
原発事故の惨禍の中、必要な情報が届かずに危険な現場へ赴き、必要のなかった被ばくを強いられたこと。
「危険である」ことだけはわかっているが、その危険性の詳細は伝わらないのだ。人を助けに行く人に身を守るための情報が届き、人を助けに行く人が最も守られてこそ、その外側の多くの人が救われるはずだ。「災害の二次被害を真っ先に受けるのは、消防です」と話してくださった消防士の顔がなんども脳裏に浮かぶ。
それだけではない。
2月22日には、船内の業務に携わった医師や看護師、検疫業務にあたった職員やDMAT(災害派遣医療チーム)などの医療関係者を、検査の対象から外す方針も明らかになった。その理由を、厚生労働省は「感染を予防する技術を習熟し、十分に対策しているから」としているが、すでに検疫官とDMATなど船内で業務にあたった人が感染しているのだ。最前線で尽力する人をないがしろにする、信じがたい話だ。
この報道でも、彼らを思い出した。原発事故直後、「病院搬送する傷病者はスクリーニング場で検査を受けたが、私たちは受けず、病院内に入らない措置がとられた」と話していた。そのため、彼らは自分たちで検査をしていたが、公的に設置されたスクリーニング場での検査記録数には含まれていない。
また、日本災害医学会によると、新型コロナウイルスに対応した医師や看護師らが職場内外で、バイ菌扱い、子どもの登園自粛を求められるなどの差別的な扱いを受けたという(2月22日・報道)。これもまた、多くの双葉郡の消防士たちが経験したことでもある。懸命に活動した現場の人々の疲労はピークに達しているはずだ。そのことに対し、敬意を示すでも、いたわるのでもなく、心をも攻撃する差別が繰り返されている。
そもそも、感染者が出てしまったら案ずるのが当然で、差別など許されない。しかし一方で、詳細な情報を開示しないこと、検査を積極的に行なわないこと、適切な対応をしないことで、世間が疑心暗鬼になっていることも事実だ。その点で、こういった差別は、国の対応のまずさが一因となり引き起こされたといえる。
そして、感染の可能性があっても、一定の症状や条件を持たない限り検査をしてもらえない、という悲痛な声もSNSに散見される。検査をしないことには、実際の感染者数がわからない。積極的に検査を行なわないことで、感染者が「いない」ことにされてしまう。
原発事故直後においても、初期被ばくの検査が適切に行なわれなかった。また、積極的に把握しようとしない、定義を変えて数字から外してしまう原発事故の避難者数や子どもの甲状腺がんの患者数のことも想起させる。
今後、新型コロナウイルスが蔓延すれば「致死率」で語られるようになるのだろう。その致死率の中で亡くなるたった一つの命は、確率の概念では語れない。
クルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス」の中に留め置かれた人々、そこで対応に当たった人々は、世間に可視化されない船内の状況を事細かに記録してほしいと思う。これも原発事故同様、双葉郡の消防士たち同様に、「なかったこと」にされてしまいかねないからだ。
まさか、この原稿がこういった内容になるとは、数週間前にはまったく考えてもいなかった。2011・3・11の出来事から、原発事故の被害を受けた人々から何も学ばなかったのだろうか、と絶望的な気持ちにさせられている。
取材時には見えていなかったこと――A4の一枚の紙
前置きに力が入ってしまったが、『孤塁――双葉郡消防士たちの3・11』発刊の裏話的なことを書きたい。
改めて、2018年10月から通った双葉消防本部の70人近い消防士からの聞き取りノートを見返していた。一人一人のページに名前のインデックスをつけたノートは、10冊になった。書ききれなかったことが、これほどあったのか、としみじみ思う。
ふと開いたページに、「2011年3月から2016年2月までの自家用車の走行距離が、21万キロになった」という松本孝一さん(43・浪江消防署葛尾出張所主査/当時)の言葉があった。福島県外に避難をした家族に会うために、休みの日に行き来した距離だ。その数字からも、避難の苦労と家族への思いが伝わる。東日本大震災の直後、半年後、1年後、その時その時で、より良い選択をしようと思いながらこれまでやってきたが、それが本当にベストだったかどうかは、自分ではまだわからない、と胸のうちを話してくださった。
松本孝一さんにインタビューをしたとき、一枚の印刷された紙を見せてもらった。それは、葛尾村の防災無線で全村避難を呼びかける原稿だった。その言葉を、松本さんはマイクに向かって読み上げたのだ。私はその時、「ああ、こういった記録も残していらっしゃるのか」と思い、写真を撮らせてもらった。
その約1カ月後に、松本孝一さんの息子さんである敏希さんにお話を伺った。3・11後の避難のこと。3・11前の小学生の頃の、父と特訓した野球の思い出。
その話を聞いて、自宅に戻り、松本さんが全村避難を呼びかけた原稿の写真を何となく見ていて、ハッとした。敏希さんが父・孝一さんと野球の特訓をしたのは、葛尾村のグラウンドなのだ。その後、松本さんは大熊町に引っ越しをして、震災当時は大熊町の町民だったが、もともとは、葛尾村村民だった。その松本さんが、葛尾村の村民に全村避難のアナウンスをした。不眠不休で、爆発した原発の近くまで何度も救急搬送に向かい、原発構内への出動の可能性もあるなか、家族への遺書も書いた、その頃の話だ。非番の日は欠かさずに息子と野球の特訓をした、大切な思い出の残る葛尾村で、人々に「ここから去ってくれ」と言わなくてはならなかった。松本さんはどんな思いで、その原稿を読んだのだろう。どんな思いで、その原稿を手もとに残しておいたのだろう。そして、どんな思いで、私に見せてくれたのだろう。
その写真に、私の「わかっていない」ことが突きつけられている。一枚のA4の紙には、松本さんの思いが詰まっていたのだ。
どこであれ助けに行く――四号機火災の事実の前で
私の「わかっていない」ことはたくさんあった。
例えば、こんなことがあった。四号機の火災現場に双葉消防本部は3月16日の早朝に向かっているが、消防士たちは、「もう戻れないのではないか」という思いを抱えて原発構内に向かっていたのに、実際には火が消えていた。彼らのインタビューと東電テレビ会議の記録とを並べてみたところ、東京電力本店の広報が、双葉消防本部の到着の1分前に、「火は見えない」という広報を行なっていたことがわかったのだ。当時の東電広報の言葉からは、火が見えないという情報を一分一秒でも早く伝えたい様子がにじみ出ている。
そのことを知ったとき、私は涙が止まらず、怒りと悔しさで丸一日、悶々と過ごした。その事実を知っている消防士もいるかもしれないが、知らない消防士もいるかもしれない。彼らがどんな思いでそこに向かったか、どんな思いでそれを見送ったか、私はたくさんの消防士からその時の思いを聞いていたのだ。
しかし、事実は事実だ。そのことを書くと決め、実際に書いたが、事前に消防本部にも相談した。対応してくれた加勢信二さん(現・総務課長)に、「みなさんが『戻れないかもしれない』という思いで向かった四号機火災現場は、到着していた時には火が消えていた」と、怒りと悔しさをにじませて報告した。そして、そのことを知らない方もいるかもしれない懸念も伝えた。
じっと話を聞いていた加勢さんは、静かにこう言った。
「消防という組織は、どこか特定の事業所に対して、何かの感情を抱く、ということはないんですよ。どこの事業所で傷病者が出ても、その人を助けに行くんです」
ああ……、とその後の言葉が続かなかった。
私は、わかっていなかった。人を助けるプロである彼らは、私の怒りよりはるか上位に、「人を助けること」を当たり前に置いているのだ。
もちろん、一人一人にさまざまな思いがあるだろう。言えないこともたくさんあるよ、と話してくれた消防士もいる。それでも、それが仕事だと。人を助けたくて、人の役に立ちたくて消防士になった、とたくさんの消防士が話をしてくれていたのだ。
危険な現場だからこそ――双葉消防の経験を真に活かす
でも、それを知ったうえでもなお、知ったからこそなお、あえて書いておくが、届けられるべき情報が届かなかったこと、事故時の想定を甘く見ていたことで、しわ寄せが地元消防にいったことは、国と東京電力の責任だと「私は」思っている。
危険な現場に行く人こそ、守られてほしい。危険だという情報が適切に伝えられてほしい。その人たちが一番に、守られてほしいと願わずにはいられない。そのための対策や仕組みは、過剰なほどでいいのだと心から思う。
2月15日の講演で渡邉敏行さんは、私に最初に話をしてくれたように「事故原因をしっかり検証してほしい」と語った。対策や仕組みは、検証があってこそ作られる。今なお、原発事故には、検証しきれていないことが多く残されている。たくさんの人に、渡邉さんの語りが、消防士一人一人の経験が伝わり、そこから学ぶことで、二度と同じようなことが起こらない対策と仕組みが作られてほしいと願う。
そして、新型コロナウイルスの政府対応を見ながら、その願いを、身悶えするほどの悔しさに変えている。
(『世界』4月号、pp.222-225)
| 【著者紹介】 | |
|
|
吉田千亜(よしだ・ちあ) 1977年生まれ。フリーライター。著書『孤塁――双葉郡消防士たちの3・11』(岩波書店)、『ルポ 母子避難』(岩波新書)、『その後の福島』(人文書院)。 |
*『世界』2020年4月号では、『孤塁』刊行記念トークイベントの様子を掲載。元・双葉消防本部消防士の渡邉敏行さんの講演「消防とは何か? 原発事故の経験から考える――双葉郡消防士が語る3・11」にある当事者の生の声を、ぜひ本誌でお読みください。