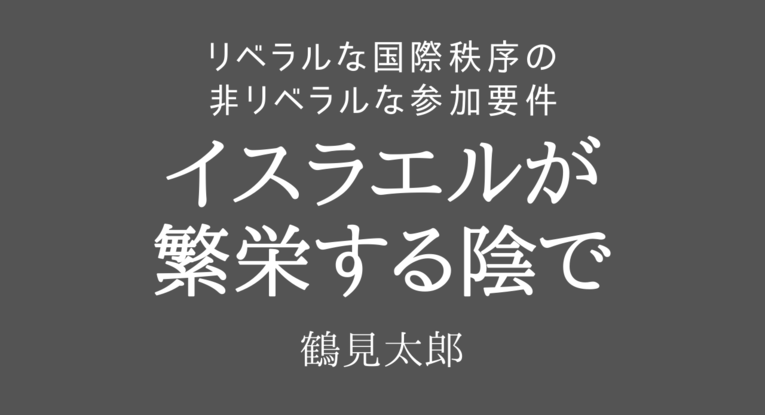〈特別公開〉イスラエルが繁栄する陰で――リベラルな国際秩序の非リベラルな参加要件
※『世界』2022年12月号収録の記事を特別公開します
リベラルな国家はリベラルな国際秩序の担い手か
リベラルな国際秩序の危機と世界的な民主主義の危機は、しばしば混同されている。現在の世界は、リベラルな国際秩序に従う民主主義諸国と、国内体制・対外政策のいずれもリベラルでない諸国や国内諸勢力のあいだの対立として描かれることが多い。
国際関係論におけるデモクラティック・ピース論も、民主主義国が増えるほど、国際秩序もリベラルになることを想定してきた。その理屈はリベラル以外の立場でも共有され、2000年代のアフガン戦争やイラク戦争に際し、ジョージ・ブッシュ米大統領は、軍事力を用いてでも国内体制を強制的にリベラルにすることを正当化した。
だが現実においては、国内体制はリベラルでありながら、リベラルな国際秩序の遵守度が非常に低い場合がある。その代表がイスラエルである。
対象をユダヤ人に限った場合、イスラエルはかなりの程度民主主義国である。『エコノミスト』による民主主義指数(2021年)では167カ国・地域中23位に位置し、これはフランスとスペインのあいだにあり、アメリカ(26位)よりも上位である。個人としての市民的な諸権利はイスラエル国籍のパレスチナ人にも適用されており、2021年に発足したベネット政権では、多数派形成のためとはいえ、アラブ系政党もイスラエル史上初めて連立入りした。
もちろん、元来この地域に暮らしていたパレスチナ人からすれば、この捉え方には瑕疵がある。彼らの意志を無視して一方的にイスラエルが建国されたという、明白ながら忘れられつつある史実を措くとしても、イスラエル国籍を持つパレスチナ人にとっては、集合的なものへの配慮(例えばユダヤ教の安息日に公共交通機関が止まるなど)がユダヤ人のみに適用されることは不公平である。イスラエルが占領する西岸地区やガザ地区居住の、さらには域外の難民といったイスラエル国籍を持たないパレスチナ人からすれば、イスラエルに生活や人生を大きく規定されているにもかかわらず、イスラエルに対する選挙権を持たないため、民主主義は一切実現されていない。まさにこの部分に、イスラエルのリベラルさと非リベラルさの境界がある。
国際法の観点からも、1948年のイスラエル独立までの過程やその後度重なった戦争を別にしても、西岸・ガザの占領地そのものやその運用の仕方に関してイスラエルの違反の程度は著しい。例えば、国際的に承認された国境であるグリーンラインを超えてユダヤ人入植地を拡大させ、その一部を国内法では一方的に併合しているし、パレスチナ人の暗殺を繰り返してきた。西岸では多くの検問の設置と監視体制によって人々の日常的な移動が阻まれて経済は疲弊し、ガザでは封鎖によって人道危機が続く。
では、イスラエルの国内体制と対外政策のこの落差は何に起因するのか。また、なぜ現行の国際秩序のなかでパレスチナ人の苦境は終わらないのか。
すぐに思いいたることとしては、リベラルな国際秩序の守護者とされるアメリカの同盟であることが、リベラルな国際秩序の側かどうかの判断基準になっている傾向があり、こうした事態が看過されやすかったことが指摘できるだろう。しかし本稿は、リベラルな国際秩序への参加要件がそもそもリベラルな原理に基づいておらず、そのサークルの外側に位置する場合にはリベラルな原則が適用されないという二重性に着目したい。
この参加要件を一言でいえば、「ネーション(国民/民族)であること」である。イギリスの外交官として国際連盟に関わったこともある国際政治学者E・H・カーは、1945年の著書のなかで、次のような懸念を表明している。ナショナリズムに基づいて国家の数が急増した第一次世界大戦後の「国際秩序」は、「その基礎として、個人の権利をネーションの権利に沈めることを是認した」(1)。この問題は今日まで残り続けており、以下では、イスラエルに関連してこれが何を意味するのかを見ていきたい。
イスラエルの起源――帝国秩序から国際秩序へ
今日のイスラエルの支配層の多くは、ロシア東欧地域から移民してきたユダヤ人とその子孫である。20世紀初頭の段階で、世界のユダヤ人口約1000万人のうち約520万人がロシア帝国に、200万人がオーストリア・ハンガリー帝国に暮らしていた。ロシア帝国で19世紀末にユダヤ人に対する迫害事件(ポグロム)が吹き荒れたことを契機に、パレスチナにユダヤ人の民族的拠点を打ち立てようとするシオニズムが生まれた。
民主主義の伝統を持たないこれら地域からやってきたユダヤ人による新興国家が短期間のうちに民主主義体制を構築できた主な背景は次のようなものが考えられる。まず、差別・迫害の経験や建国直後に始まる戦争に伴う国民総動員体制による国民の団結や、移民が先住民の社会を無効化したうえに建設した国家であるために地主や伝統支配層のしがらみがなかったことが挙げられる。
また、歴史的に見て、武力を持たないユダヤ共同体は、帝国におけるマイノリティという条件下で、ユダヤ人に固有の仲介人的な役割を活かしながら政府や周囲と協調する一方で、共同体内ではユダヤ教を核としながらお互いに助け合っていた。階梯構造を持つ教会組織のようなものはなく、各共同体は自律的に運営され、男性に限定されていたとはいえ、指導層は選挙で選ばれることもあり、そうでなくてもユダヤ教に関する知識の豊かさを基準に、世襲ではない形で選ばれていた(2)。シオニストの中心は啓蒙主義の影響を受けた世俗的な人々であり、ユダヤ教に縛られることさえなく、そうした緩やかな民主的な土壌のみを受け継いだのである。
そのようなユダヤ人の存続を至上命題としたシオニストが踏まえていた国際秩序観は、まさに彼らがパレスチナに宗教的拠点ではなく「ナショナルな」拠点の設置を目指したことに表れている。シオニストはユダヤ人を宗教集団ではなく、フランス人やドイツ人に比類する「ネーション」と定義した。当時のロシア帝国でネーション概念はまだ一般的ではなく、西中欧で一般化しつつあった概念を先取りした部分もある。シオニストは、ユダヤ人ばかりが差別される原因を、ユダヤ人がネーションとして尊重されておらず、賤民として蔑まれていることに求めた。
その後オーストリア・ハンガリー帝国は諸国民国家に分裂していき、ソ連においても集合単位はネーションに準じる概念に基礎が置かれた。例えば、ウクライナ共和国では、ウクライナ民族が中心に位置づけられた。関係地域内外の秩序の変化について、シオニストの想定は当たっていたといえるだろう。ネーションが国際社会の基礎単位であり、各ネーションは自前の国家を持つとの論理は第一次世界大戦以降の「国際社会」における基本原則となった。国際連盟はLeague of Nationsである。
もとよりユダヤ人はネーションとしてまとまることに関し、かなり有利な状況にあった。長きにわたりユダヤ人/ユダヤ教徒としてまとまって社会を構成していたし、伝統的に受け継がれてきたユダヤ教は、世俗的なユダヤ人にとっても統合の象徴になりえた。周囲も、ユダヤ人の一体性を時に過剰なまでに認めていた。
パレスチナ人にとってのネーション
だが、ネーションを参加要件とする「リベラルな国際秩序」の基本原則は、リベラルな原理によって決まったわけではなく、西欧固有の事情のなかで確立していったローカル・ルールにすぎない。そもそもフランス革命時の「ネーション」と、東欧以東で発展したそれとでも意味合いは異なっており、文脈依存性が高い概念である。
19世紀から20世紀にかけてのパレスチナにおいて、「アラブ人」はアラビア語を話す人々という程度の意味であり、部族や村、宗教・宗派の別のほうが日常的にも行政的にも重みを持っていた。そもそも、このアラブ人のなかにユダヤ教徒が含まれることは通例だった。一方、シオニストはあくまでもアラブのユダヤ教徒も含めて「ユダヤ民族」としてこの地域でまとまろうと意気込んだ。オスマン帝国崩壊後にこの地域を、それこそ国際連盟からの委任統治という形で統治することになったイギリスは、宗教(イスラーム教やキリスト教)を基礎単位として法整備を行った。もっとも、ユダヤ人は民族基準でも宗教基準でも同じ範囲のまとまりになるから、団結のしやすさでユダヤ人がはるかに有利だった。
「ネーション」は、「エスニック集団」と異なり、政治的にまとまり、自集団を自ら統治する能力を持つ集団であることが含意された概念である。そのことに関し、非ヨーロッパ人は偏見を持たれやすかった。パレスチナが「委任統治」となったのは、まさに、アラブ人に自己統治は「まだ早い」と国際連盟が判断したからである(「早さ」にも序列があり、アフリカ人はさらに未熟とされた)。
シオニストは、パレスチナに暮らす非ユダヤ人の存在を無視していたわけでは決してなかった。問題は、シオニストが彼らを独自のネーションとはみなさず、「アラブ民族」の一部と捉えたことにあった。シオニストは、他の広大な土地を持つアラブ民族は、パレスチナという小さな地域ぐらい譲るべきだという姿勢でいた。だが当の先住民からすれば、シリアやイラクの人々と等価とされる論理は「言語明瞭・意味不明」だっただろう。
政治共同体としての土壌を持ち、大枠では同じ目的で一致していたシオニスト・ユダヤ人に対して、突然流れ込んできた彼らへの対処を迫られたパレスチナ人に、ネーションとしてまとまってシオニストと対等に張り合うよう求めることは酷だったはずだ。だが、アラブの指導層は流行のネーション概念を批判するよりも民族自決の原則に訴える戦略をとったし、パレスチナの様々な人々も、巨大勢力と戦ううえでそれと連携する道を選んだ。それによって、パレスチナの農民も商人もベドウィンもみな「アラブ民族」という大きな括りの一部とみなされる傾向はさらに強まってしまった。
シオニストにとって、この流れは好都合だった。できたばかりの国際連合(United Nations)をはじめ、世界はパレスチナをめぐって「ユダヤ民族」と「アラブ民族」が争っていると捉えた。1947年に採択された国連パレスチナ分割決議案は、あくまでも「ユダヤ人」と「アラブ人」をそれぞれの中心とする「ユダヤ国家」と「アラブ国家」に分割することを求めた。
イスラエルのリアリスト外交と対パレスチナ政策
ロシア東欧の帝国における協調関係に見切りをつけたシオニストの外交姿勢は、決してリベラルなものではなかった。ネーションという鎧を身にまとったうえでその存続を図ることを基本原理とした。国際連盟による少数民族保護政策が形骸化し、果てにはホロコーストが吹き荒れたヨーロッパを尻目に、シオニストはその姿勢をますますかたくなにしていった。アラブ諸国が分割決議案を拒否するや否や、イスラエルは武力で独立を達成した。その後も武力を強化し、アラブ諸国がなかば折れる形となっていく。
自らに有利な環境を外交によって構築することにも余念はなかった。アラブ諸国と交戦していた時期でも、イスラエルは中東の非アラブ・非イスラーム勢力との協力関係を築き、トルコやイラン(革命前まで)、あるいはレバノンのマロン派キリスト教徒とのパイプを持っていた。1979年にアラブの雄エジプトと平和条約を、一九九四年には最も長く国境を接するヨルダンと平和条約を結んだ。2020年には、UAE、バーレーン、スーダン、モロッコと立て続けに国交を正常化させていき、イランを共通の天敵とするサウジアラビアとも水面下では蜜月関係にある。
アメリカの意向にも沿ったこうした協調姿勢はリベラルにも見えるかもしれないが、問題の最大の焦点であるはずのパレスチナ人にとっては、連帯仲間や庇護者からの切り離しを意味した。事実、これらの和平合意において、パレスチナ難民、占領と入植地、エルサレムの地位のいずれの問題も取り決められなかった。
もちろん、イスラエルも建国来パレスチナ人を無視し続けてきたわけではなかった。イスラエルのなかでは、1970年代に入るころから、国家の安定化がある程度達成されたことをもって、パレスチナ人との歩み寄りを目指す機運が生まれつつあった。1993年に結ばれたオスロ合意はその一つの到達点でもあり、力一辺倒な国家でもリベラルになりうることを予感させた。
だが、そこにもリベラルな国際秩序の陥穽が潜んでいた。
西岸・ガザがイスラエルの占領下に入ったのは1967年の第三次中東戦争での大勝の結果である。それ以降、直接パレスチナ人を統治することには様々なコストがかかり、特に1987年のインティファーダ(蜂起)により、国際的な非難も高まった。パレスチナ人を一つのまとまりとして自己統治させることは、コストの削減にもなると考えられた。
仲介役としてオスロ合意を導いたノルウェーやアメリカも、パレスチナ人を一つのネーションとして捉え、イスラエル国民との和解という構図を作っていった。もちろん、パレスチナ人を独立したネーションと定義することはほかならぬパレスチナ人自身の悲願ではあっただろう。
しかし、ネーション同士の交渉という体になったことで、パレスチナ人の窓口はPLOに一本化され、パレスチナ人の多様で複雑な状況は過度に単純化されることになった。当時、イスラエル占領がパレスチナ社会に引き起こした変化も相まって、ハマースなどのイスラーム系新興勢力が伸長し、インティファーダでも存在感を示していた。PLO(パレスチナ解放機構)議長にしてその主流派ファタハを率いるアラファートは、これを脅威に感じていた。湾岸戦争でフセインを支持した外交的失点も響いていた。イスラエルと和平を結ぶことで政治的基盤を再強化したいとの思惑のもと、アラファートはイスラエルに対して大きな譲歩を行ったのである。難民問題は事実上棚上げされ、自治についても暫定自治がごく一部地域で開始されたとはいえ、残りは見通しが示されるにとどまった。
こうしたオスロ合意に対してはPLO非主流派にくわえ、ハマースなどの新興勢力も反対を表明し、イスラエルの違反や欺瞞がやがて明らかになると、イスラエルに力で対抗していくようになった。
他方、ネーションとしての一体感が強いかに見えたイスラエルにおいても、オスロ合意を締結したラビン首相が1995年に宗教右派のユダヤ人に暗殺されたことが象徴するように、オスロ合意を過度な妥協として非難する動きは小さくなかった。主権を持つネーション同士が対話して解決を図るというリベラルな国際秩序の原則に立ったオスロ合意は、その形式から溢れ出た別の諸層の反乱によってものの数年のうちに瓦解していったのである。
とはいえ、これで振り出しに戻ったわけではなく、パレスチナ自治政府とその範囲をネーションに見立てた構図は続くことになった。国境や税金、安全保障はイスラエルがほとんどを管理する状況は変わらなかったにもかかわらず、パレスチナ人をイスラエルとの交渉へとまとめることは自治政府の責任とされた。だがその建前に従うパレスチナ人は多くなかった。ハマースやイスラーム聖戦などの諸組織はイスラエル市民に対するテロを繰り返し、それを止められないことに対してアラファートは責められ(また、イスラエルは一般市民を巻き込む「報復」攻撃や暗殺を繰り返し)、パレスチナ人のネーションとしての不全さが論われることになった。
パレスチナ人からすれば、そもそもシオニストに土地を奪われたうえに抑圧体制下に置かれ、穴だらけのオスロ合意を結ばされ、当初の淡い期待もすぐに裏切られていくなかでの決死の抵抗だった。絶望の淵にあった若者をハマース上層部が焚きつけてテロを促すという、占領下ゆえの歪んだ社会構造もあった。
だが、イスラエルのユダヤ社会は、パレスチナ人はやはり信用ならない、言葉が通じないテロリストだとして、再び、あるいはそれまで以上に態度を硬化させていった。分離壁と無数の検問に象徴されるように、実力行使と徹底した監視・管理によってパレスチナ人の動きを封じ込めることがテロを防ぐ最善の策とされるようになる。その一方で、入植地の建設は着々と進んでいった。
パレスチナ自治政府は、2007年には自治政府・ファタハが実効支配する西岸と、ハマースが実効支配するガザに分裂していく。2006年の選挙で、イスラエルや欧米諸国がテロ組織とするハマースが、腐敗が進むファタハの対抗馬として大勝したことが契機となっている。この分裂状態はイスラエルが本格的な交渉を棚上げする口実となっているが、ネーション本位の「リベラルな国際秩序」はこの状態の処理方法を知らない。
セキュリティの同盟と資本としての占領地
アメリカにとって、イスラエルはしばらくのあいだ同盟国ではあってもリベラルな国際秩序における模範ではなかったはずだ。アラブ諸国がソ連に傾くことを警戒してイスラエルと一定の距離を保っていたアメリカが関係強化に舵を切ったのは1970年代である。中東をめぐる米ソの対立が激化するなか、イスラエルが中東の親米勢力を支援しうる域内大国となったからである。
それでもパレスチナ問題の解決はアメリカにとっての重要な関心であり続けたが、イスラエルにその意向を従わせるコストとリスクには限りがあり、イスラエルへの資金・武器援助と引き換えに、和平交渉のテーブルにつかせることや入植地建設を一時的に凍結させることが関の山だった。
だが2001年の9・11はこの構図を変えた。「対テロ戦争」である。当初こそアメリカはアラブ諸国の協力が必須と考え、パレスチナ問題の解決にも意欲を示した。しかしそれ以上に、イスラエルの「テロと戦う」姿勢と経験にアメリカは引き寄せられていくことになる。ブッシュ政権が民主主義の推進を重視したことも、「中東で唯一の民主主義国」イスラエルには好都合だった。アメリカから見て、イスラエルはリベラルな国際秩序の問題児から、それを守るためのキープレーヤーへと変貌したのである。
国家間戦争を防ぐことに国際政治の主眼があった時代に重視されていたのは、各国の体制や外交政策がリベラルであることだった。他方、「対テロ戦争」において、当初こそ「テロ支援国家」の民主化が重視されたものの、それが実現困難であることもあり、情報の共有や水際対策など、ミクロな監視と管理に関心は移っていった。
そこで重宝されるようになったのがイスラエルのセキュリティ技術である。もとよりイスラエルは武器の輸出大国である。2017年からの五年間で見ると、世界の武器輸出のシェアでイスラエルは、スペインに次ぐ第10位(2.4%)に位置する。地域別ではヨーロッパ向けが増えているほか、湾岸諸国が主要な輸出相手となっている。
軍需産業との相乗効果によって、イスラエルではハイテク産業も発展した。世界的に需要が高まった1990年代から2000年代初頭にかけて、高学歴者や技術者が多かった旧ソ連からの120万人もの移民(当時のイスラエル人口の2割に相当)が流入し、人的資源を提供したことで、特に情報通信技術産業では1990年から2001年にかけて、イスラエルのGDPに占める割合は5倍に増えた(3)。2000年代において、ハイテク産業全体がイスラエルのGDPに占める割合は世界で最も高い13%であり、イスラエルの輸出の31%を占める(4)。ナスダック市場における米以外の企業298社のうち67社がイスラエル企業である(2008年)。
そのなかで目立つのが、国土安全保障(homeland security)分野の企業である。これはイスラエル同様にハイテク産業が盛んな台湾やインドでは見られない現象である。この分野の企業の経営陣には治安部門出身者が多く名を連ね、製品が実地での豊富な経験に裏づけられていることが謳われている。同産業はイスラエルの外交的躍進を大きく後押しした。近年急速に進んだアラブ諸国との関係改善の背景でもあるし、国内で様々な治安の問題を抱えるインドも、テロ対策で実績のあるイスラエルとの関係強化を図っている。何より、それまでイスラエルに軍事支援を行ってきたアメリカが、今度はイスラエルの技術や経験を模倣するようになったことも指摘されている(5)。イスラエルの訓練施設を使ったアメリカ軍とイスラエル軍の共同演習も増え、2007年に両国は国土安全保障協力覚書を交わした(6)。
セキュリティ分野の技術は、実際にイスラエルの占領地で使用されてきたものであり、例えば、マガル・セキュリティ・システムズ社は、侵入者を検知する囲い関連の技術を、西岸におけるフェンスや堀に参画することで培ってきた。この分野で世界の4割のシェアを持ち、米トランプ政権の目玉だった米墨国境のフェンスを請け負ったことで知られる。2008年の北京オリンピックでは、複数のイスラエル企業がセキュリティ関連で参画した。ナイス・システムズ社は地下鉄駅のセキュリティ網の更新を請け負い、DDS社は10の関連施設のドア監視を担当した。監視技術はサッカーのフーリガン対策として売り出されたりもしている(7)。皮肉にも、国際的な非難の対象である占領地は、輸出技術のための「実験場」としての資本になったのである。
国土安全保障については、技術の次元にとどまらず、背景にある考え方とセットで捉えるべきである。「対テロ戦争」に際して、アメリカではイスラエルの経験から学ぶことが唱えられてきた。例えば人権法に関して、イスラエルはガザや西岸において、テロの脅威ゆえに、十全に適用されないこともやむをえないとの理屈を立ててきた。この理屈はアフガニスタンという「失敗国家」においても参考にされている。また、米フーバー研究所のある研究員は、「イスラエルの経験は、アメリカの九・一一以降の状況における対反乱〔insurgency〕・対テロ作戦を遂行する際の戦術や技術に関して、歴史的な記録や実験室を提供している」と評した(8)。
つまり、いまやリベラルな国際秩序の側に、イスラエルの知見や思想が逆流するようになっているのである。リベラルな国際秩序に関する伝統的な考え方が、世界の人々の政治環境の改善が国際秩序をよりリベラルなものにするとの見通しを曲がりなりにも持っていたとしたら、イスラエル流の考え方は、既存の秩序を反乱分子の侵入をミクロに防ぐことで維持しようとするものである。自らの繁栄を壁で囲って守り、そのことによってその外側で何が起こるかには頓着しないゲーテッド・コミュニティ(アメリカやブラジルなどに見られる、周囲を塀で囲み住民の出入りを管理することで治安を高めることを狙った高級住宅地)の考え方に似ているかもしれない。
国際秩序の記憶
以上のようなイスラエルの現状が、様々な意味で、国際秩序が背負ってきた歴史の帰結であることは想起しておきたい。ロシア帝国で19世紀末から革命後の内戦期までに吹き荒れたポグロムは今日までほとんど清算されてこなかったし、ホロコーストに対する補償も、「主犯格」ドイツ(西ドイツ)が部分的に行ってきたにすぎず、主な「犯行現場」となり「共犯者」が多くいたはずの東欧や旧ソ連諸国においては、ホロコーストはほとんどナチス・ドイツの犯行として記憶されるにとどまる。シオニズムが本格化したのはホロコーストよりも前の時期であり、ポグロムが大きな契機となっていた。ポグロムの記憶はユダヤ人に対する暴力を何であれ謂れのない迫害と認識する思考回路を醸成し、パレスチナ人の、シオニズムが契機となった生活苦に起因する蜂起の意味を軽視することにつながった(9)。
国際秩序に関する加害/被害の記憶は、アメリカやソ連が絡む場合はある程度議論されてきたが、超大国が絡まないものについて、その長期的影響までを視野に入れた検証はほとんど手つかずのまま残されている。国際秩序は記憶する主体ではないかもしれない。だが、「ゲーテッド・ネーション」とでもいうべき在り方がイスラエルから生まれ、拡散したのはなぜかを考えるとき、またそれがその外側に存在する諸個人の人権侵害のうえに成り立っている状況を鑑みるとき、国際秩序の来歴は無視できなくなるのである。
注
(1)E. H. Carr, Nationalism and After, London: Palgrave Macmillan, 2021, p. 35.
(2)Shlomo Avineri, “The Historical Roots of Israeli Democracy,” Shofar 6(1) , 1987, pp. 1-6.
(3)Neil Gandal et al., “The High-Tech Sector,” in Avi Ben-Bassat et al. eds., The Israeli Economy, 1995-2017, New York: Cambridge University Press, 2021, p. 533.
(4)Assaf Razin, Israel and the World Economy:, Cambridge: The MIT Press, 2018, pp. 99, 107.
(5)Stephen Graham, “Laboratories of War,” in Elia Zureik et al. eds., Surveillance and Control in Israel/Palestine, London: Routledge, 2011, p. 135.
(6)Efraim Inbar, “US-Israel Relations in the Post-Cold War Era,” Eytan Gilboa and Efraim Inbar eds., US-Israeli Relations in a New Era, London: Routledge, 2009, pp. 44-45.
(7)Neve Gordon, “Israel’s Emergence as a Homeland Security Capital,” in Elia Zureik et al. eds., op. cit., pp. 153-165.
(8)Stephen Graham, op. cit., pp. 136-137.
(9)この点について筆者はさらに検証中であるが、暫定的な成果として以下を参照。鶴見太郎『イスラエルの起源――ロシア・ユダヤ人が作った国』講談社、2020年、182―212頁。