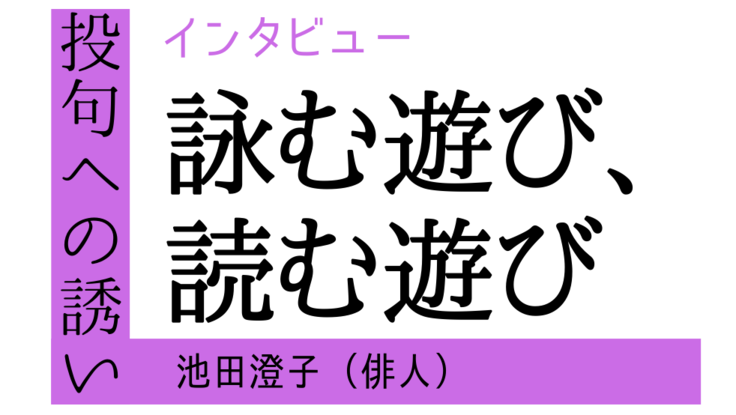インタビュー 詠む遊び、読む遊び――投句への誘い
――池田澄子さんは、つねに新しい感覚を求めている俳人であり、その句はいま若者からも人気があります。俳句について思うところを、澄子さんにお話しいただきました。
俳句へのときめき
池田 中学に入ったときの担任の先生が、後ろの黒板によく短歌を書いていたの。私、それを読んでとっても感動した。家に帰ってからそれを母に言ったら、それは啄木よ、と。そこで、どうしようもない、放っておけない人を知ってしまった。枕の下に啄木の本を置いて寝たりもしたわ。夢を見ないかと思って。書かれたものから心ときめかされた、初めての経験だった。俳句には、ときめく機会がなかった。
三七、八歳くらいの頃、ふとしたきっかけでおばあさんの俳人にご縁ができて、初めて俳句らしいものを作って見ていただくことになった。すると、「ああこれは観念ね」とおっしゃった。書かれるものは観念だと思っていたから、俳句は観念じゃないということを知って、とても驚いたわ。それで火がついて、本を読んでみようと思って本屋さんをのぞいたら、『俳句研究』(一九三四年に創刊され、現在は休刊となっている俳句雑誌)が置いてあって、そこに阿部完市の句が載っていた。こういうのも俳句なのかと思って、俳句について全く誤解していたと感じたの。
その後東京に引っ越して、どこかで俳句ができないかしらと探したら、ちょうど自宅の近くに感覚に合う俳句結社があった。それが「群島」(主宰は堀井鶏(けい))だったのね。旧い句を作る人もいれば、オシャレな句を作る人もいて、先生のやり方を押しつけるようなことはなく、自由にさせてくださるところだった。だからとても居心地が良かったのだけれど、もっとしゃかりきにやりたくもなってきた。
そんな折、『俳句研究』の特集で見つけたのが三橋敏雄だった。三橋先生は結社を持っていないから、とにかく手紙を出すしかない。なかなか踏ん切りがつかなくて四、五年経ってしまった。実行力がないのね、私(笑)。ようやく決心して手紙を書いたら、何でもいいから五〇句持ってきなさいとお返事が来た。何とか集めて持っていったら、一句一句選評してくださったんだけど全然ダメなの。辛うじて五句、捨て句(句集を編む際、本気の句ばかりだとくたびれてしまうので、美味しい箸休めといった趣をもたせて混ぜ込む句)にいいよ、と言われたものがあったくらい。そのうちの一つは「花なずな胸のぼたんをひとつはずす」だったかしら。
そして、三橋先生が所属していらした『俳句評論』(高柳重信が創刊した俳句同人誌)の句会に参加した。そこで私は俳句の読み方、詠み方を学んでいったわね。『俳句評論』の女性俳人たちの句が、またかっこいいのよ。黄泉(よみ)が見えるような句だったり。『俳句研究』で毎年高柳重信が選んでいた「五〇句競作」というものがあったのだけれど、そこに並ぶ句もみんなよくて、それにも刺激された。「クレヨンの黄を麦秋のために折る」(林桂)といった句などね。ここに出せるようになりたいと思って励んだわ。
そうして三橋敏雄のところに行くようになってから、堀井鶏に挨拶に行ったの。普通は他の結社とかに行ってしまうと冷遇される。でも彼は違った。「『真神』(三橋敏雄の句集)がちょうどぼくのところにあるから、持っていきなさい」と下さった。きっと堀井鶏は三橋敏雄をいいと思っていたんでしょうね。紳士でいい先生だったんだなと、今になるとなおさら思う。最初に堀井鶏に出会って、そこから三橋敏雄につながっていったのは、本当に運命だったわ。

何を詠むか
池田 俳句を真剣にやるようになって、かっこいい作品に引っ張られないようにするのが大変だった。新しいものが作りたかったからね。かっこよくないほうに、鈍くさくいこうと意識したとき、「ちょっといまごはん食べてきた」みたいな調子でぽろっと出てきたような句は、いままでなかったんじゃないかなと思った。それで、そういう句を作り始めたのね。
私の俳句は口語俳句だと言われるけど、口語俳句を作ろうと考えたことは実は一度もないの。普通の言葉で作ろうとしていただけで。ただ、俳句は五七五の一七音しかないから、どこかでビシッと決めるものがないと、口語では余計に、寝言を言っているようになってしまう。この、全体を締めるポイントが難しいのよ。その一つが季語かもしれない。
ただ、正岡子規は「俳句は四季の題目を詠ず。四季の題目無きものを雑(ぞう)という」(『俳諧大要』岩波文庫)と言っていて、四季の題目が無い句を詠むなとは言っていないのね。でも、「雑の句は四季の聯想なきをもってその意味浅薄にして吟誦に耐えざるもの多し」とも書いている。たとえば花の名前を一つ入れれば、少なくともその花の意味や季節感は伝わっちゃう。一方雑の句は、季節感どころか何も伝わらない可能性もある。有季俳句でも、何も言いたいことが無い、まるで無意味な句はあるけれど、無季俳句の場合は、季語に替わる何かしらの主題、伝わるものがないと成り立たないと思う。何も無いのが面白い、ということもあるかもしれないけどね。三橋敏雄には、「待遠しき俳句は我や四季の国」という無季の句があるけれど、ここには大きな主題がある。だから、私が無季俳句をつくるときはつい重くなる。季節感も何も無いのに、軽いこと言われてもねと感じちゃうから(笑)。
私が戦争句を無季語でつくるのは、戦時中に亡くなった父の向こうにある「戦争」それ自体を、具象に基づいていろんな側面で書かなければいけないと思っているから。私の句に「戦場に近眼鏡はいくつ飛んだ」があります。父は病院で亡くなったから、現実の父の眼鏡は飛んでいないけど、戦争で飛んだのは、老眼鏡ではなくて近眼鏡。
俳句の「作法」
池田 俳句は基本的に何でもありだとは思うのね。こうじゃなきゃダメ、ということではなくて。ただ、「作法」はある。
俳句を始めた若いインテリに、作り方について六つアドバイスをしたの。「知識を表に出さない」「常識を忘れる」「季語の説明をしない」「かっこよくしようとしない」「自分を素敵に思わせようとしない」「(何故この句を作ろうとしたのかという)自分の思いそのものを書かない」。特にこの最後の点はなかなか難しい。自分がAというものを見て、Bと感じたとしても、そのBまでは書かないで、Aを見たということだけを書く。三橋敏雄も、おいしいところは読者にとっておく、とよく言っていた。何を見たのかという対象だけを書けば、読者にはそれについて感じる余白が残されるわけだから。でも、どう感じたのかをつい言いたくなっちゃうのよね。伝わらないかもしれない、とも思っちゃうし。そこは、読者を信じることが大事。案外読者はわかるものなんです。
私が最初に「観念ね」と言われたのは、たぶん私が思いを書いてしまっていたから。物や景を描写しなさい、というアドバイスだったと思う。すごく真面目な人は、どこかでバカにならないとだめなのかもしれないわね(笑)。そういう人は、これが正しい、こう感じているんだと、とても丁寧に説明してくれるのだけれど、そうすると、読み手は他のことを感じる暇が無いの。鑑賞の愉しみがなくなっちゃう。雑誌とかへの投句は、余計に説明的になっちゃうかもしれない。顔の見えない人に評されるわけだから。
前書き(俳句の前に付す短い説明の言葉)なんかもそうね。私は前書きをつけたことはないのだけれど、これは三橋敏雄の主義でもあった。一句に何かの説明をしなければわからないようであれば、その時点でその句は完成していない、と。追悼句なんかでもそう。「誰々に」とか。誰に向けたものかなんて、わからなくてもいいの。他の人に置き換えたら通じないようでは、ある意味作品として弱い句になってしまう。その人のために、ということであれば、その人にだけ贈ればいい、とも言えるかしら。高柳重信が亡くなった時に、三橋敏雄は「死に消えてひろごる君や夏の空」という句を詠んだ。もちろん重信のために書いたけど、こういう感覚は全ての人に通じるもの。この句、とってもいい句だと思うの。個人を超えて、誰かを亡くした人みんなに共感してもらえるから。
驚いて喜びたい
池田 飯田龍太が毎日新聞の選をしていたときに、実は投句をしていたことがあって。龍太らしくない句が特選になったりして、面白かった。選ばれるとやっぱりうれしかったわね。お姑さんも、掲載された私の句を近所で自慢して(笑)。
新聞や雑誌への投句は、選ばれると励みになる。選ばれるために努力もする。ただ、選者に合わせて作ってはダメだと思う。たとえば私に対してだったら、口語で軽い感じで作ればいいんじゃないか、と思ったら大間違いなの。私は結構選ぶ範囲を広くしているわ。私の句と違う雰囲気なら、それをむしろ喜ぶ。上手でないとしても、こんな書き方があるんだと驚けたら、楽しくなる。仮に選ばれなくても、それはそれでよいのです。何故かを考えるきっかけになります。
桜だったら「散る」=「儚い」といった、季語の本意を踏まえる、というのは常識でもあるわけよね。私は新しい感覚があってもいいと思う。生まれて初めて見た、触ったらどう感じるか、ということを詠み、読むのが私の理想。それは知識とは違うわけだから。みんなが知っているような知識を教えてくれても、仕方ないと思うの(笑)。大人は大体のことを知っているから、うぶな気持ちで見るってなかなか難しいけど、そういう感覚でできた句に出合うとうれしいよね。歴史や常識を背負ったものもあれば、そこからは離れた気持ちもある。それを大事にしたいなって。
俳句は「志して至り難い遊び」(『まぼろしの鱶』あとがき)と三橋敏雄も言っていた。俳句は志高い遊び。甘い相手ではないということね。
※この記事は『世界』2017年9月号に掲載されたものです
※投句はこちらから