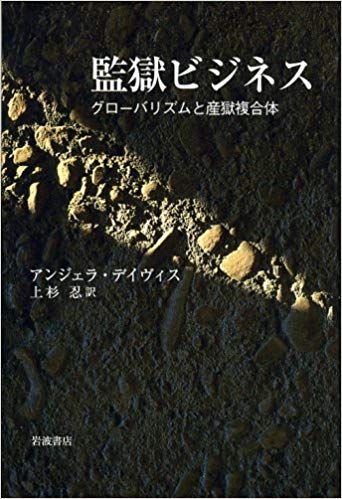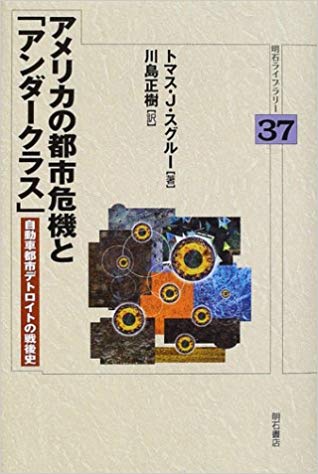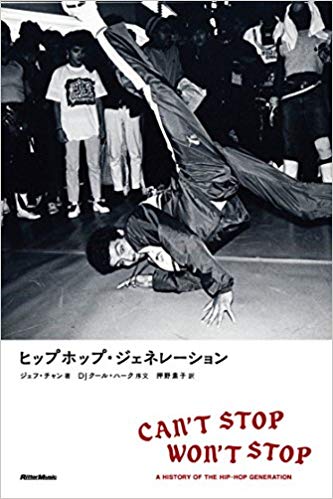テーマ書評/棚づくり 第2回 アメリカ黒人の抵抗 評=藤永康政
お馴染みの光景
『フルートヴェール駅で』という映画をご存知だろうか。
監督はライアン・クーグラー、主演はマイケル・B・ジョーダン、2013年にサンダンス映画祭で公開され、批評家からはこぞって高い評価を得た作品である。
クーグラーとジョーダンと言えば、MARVEL映画の最新作のひとつ、記録的興業収益を記録した『ブラック・パンサー』(2018年公開)を思い出す人が多いはずだ。
だが、アメコミ活劇の痛快感とは大きく異なり、『フルートヴェール駅で』は実際に起きた事件を素材とした、それを観たものは哀しみ、そして怒りを憶えるにちがいない。
その事件は2009年の元日にカリフォルニア州オークランドで起きた。
22歳の黒人青年オスカー・グラントは、大晦日の夜のパーティから帰るために鉄道に乗った。
車内で起きた喧嘩に巻き込まれ、鉄道警察隊が事態の収拾にやって来た。
警官と乗客とのあいだでの揉み合いに発展するなか、グラントは背後から撃たれ、搬送された病院で死亡してしまう。
銃を撃ったのは「白人」の警官、グラントは武器を持っていなかった。
その後、一部始終を収めた動画がインターネットにアップされると、警官に対する批判の声が高まり始め……。
残念だが、これら一連の出来事は、わが国ですらもはや広く知られている「お馴染みの光景」である。
2009年1月とはどのような時代だったのか。
それは、バラク・オバマの大統領就任式を人びとが心待ちにしていた時期にあたる。
つまり、グラントの殺害は、「ポスト人種の時代」の到来を言祝がれるなかで起きていたことだったのである。
2009年のフルートヴェール駅、ここにはすでに、トランプの時代の「分断されたアメリカ」があったのだ。
では、ポスト公民権時代のアメリカでは、いったい何が起きていたのであろうか。
それを考えるためのヒントとなる本をいくつか紹介しよう。
監獄とアンダークラス
グラントが殺害されるまでの24時間を中心に描いた『フルートヴェール駅で』では、主人公が刑務所に収監されていた頃や、保釈後も職を得るのに苦労する模様が描かれている。
保護観察官を務めていた経歴も持つクーグラーは、このような「危機に直面した青年たち(at-risk youth)」を身近に知るひとりでもある。
現在、アフリカ系アメリカ人の受刑者率は危機的な状況にまで高まっている。この現象を黒人の歴史や社会との関連から考察したのが、アンジェラ・デイヴィスによる『監獄ビジネス』(上杉忍訳、岩波書店、2008年)である。
同書は、黒人の受刑者人口の増加が、奴隷制やジムクロウ制度の時代からの黒い身体の犯罪者化を背景として、新自由主義の時代の「ビジネス」によって強く後押しされてきたという点を明らかにする。
ブラックパワー運動の中心的アクティヴィストだった著者は、これに抵抗する途を展望している。
グラントが生まれた1980年代は、間歇的な労働と非合法ビジネスのあいだを往来し、福祉の負担となる「アンダークラス」が大きな問題となっていた時代である。
この「アンダークラス論争」は、インナーシティの住民の多くが黒人であることを反映し、どこかにかならず「人種」が暗示されるものだった。
歴史家トマス・スグルーによる『アメリカの都市危機と「アンダークラス」』(川島正樹訳、明石書店、2002年、品切)は、連邦政府の住宅行政とビジネスの多角化戦略がインナーシティの危機的な状況を生み出した過程を明らかにしたものである。
社会学者や政治学者を中心に行われていた「アンダークラス論争」に終止符を打ち、今日では同種の研究の古典となっている。
同書は、都市空間の脱工業化は戦後直後にはすでに始まっていたことを見事に剔抉する。
つまり、「都市危機」の原因とされた「アンダークラス」とは、問題の原因ではなく、その結果だったのだ。
ローカルな抵抗のスタイル
ポスト公民権時代の「黒人」の「抵抗」はこのような環境のなかから生まれる。
これに関わるものとして2冊挙げたい。
両者は、「派手」/「地味」と趣向が異なれば、セレブリティ/一般市民と考察の焦点も違っている。
ひとつは、ジェフ・チャン『ヒップホップ・ジェネレーション』(押野素子訳、リットーミュージック、2007年〔新装版が2016年に刊行〕)だ。
多文化主義時代の「文化」のダイナミズムは、峻厳な環境を踏まえないと十分には理解し得ない。
同書が語るのは、ヒップホップ世代が育った1970年代のブロンクスである。
インナーシティの非合法ビジネスとギャング、そしてそこに覆い重なるアメリカ社会の刑罰国家化、このような空間と時間のなかから、ヒップホップは生まれた。
ヒップホップに関わる類書が「タレント本」にありがちな「セレブリティの礼賛」や「自慢」に傾くのに対し、同書は、時代的な背景を織り交ぜながら、この魅惑的な「文化スタイル」の誕生とその後の展開を物語っている点に特徴がある。
もうひとつは、ピーター・スメドフ、ホリー・スクラー『ダドリー通り』(大森一輝・森川美生訳、東洋書店、2011年、品切)。
黒人、ラティーノ、カボヴェルデ系(アフリカの北西沖にある国家、カボヴェルデを出自とする人たち)、そして白人住民の主体的な参加によって、かつてマルコムXも住んでいた黒人ゲトーの再生に成功した事例の記録である。
ボストン市のロクスベリー地区で創始された「ダドリー地区再生運動」の奮闘を、運動当事者と参与観察者のジャーナリストが綴った同書は、グローバル化と新自由主義政策の下で「地域の再生」がいかにして可能となるかという問題への、ひとつの「解答」を示している。
個人の闘争の記録
ポスト公民権時代のアメリカでは、全国規模の組織が展開する「黒人運動」が後退し、黒人市民たちは、自分たち生活するローカルな場での生活の向上を求めて動き始めた。
ラッパーたちが、自分が住んでいる地域=「フッド(‘hood)」を代表=「レペゼン」しようとするのもその志向の現れであるし、デトロイト、ロクスベリー、ハーレム、ブロンクスなど、大きな黒人ゲトーに存在する市民団体もそうである。
「運動」がローカルな多様性を持つなかでは、概説史的な語りでは、この2つの特徴を捉えきることが難しい。そこではむしろ個人的な体験が役立つかもしれない。
新進の黒人ジャーナリスト、タナハシ・コーツによる『世界と僕のあいだに』(池田年穂訳、慶應義塾大学出版会、2017年)は、黒人がその息子に対して、アメリカに住む黒人の苦悩を一人称で語りかけるなかで、そこからの出口を探る。
コーツが生まれたのは、1975年、脱工業化の進むボルティモア。
その息子は、2012年にフロリダ州で起きた黒人青年射殺事件——ブラック・ライヴズ・マター運動はこの事件への抗議のなかで生まれた——の犠牲者の世代に属する。
「黒人」と「白人」という人種が構築される過程で欺瞞的アイデンティティが生まれ、それがアメリカを分かち断つ。
この模様をジェイムズ・ボールドウィンを思わせる美しい筆致で綴る同書は、ポスト公民権時代の黒人の「闘争(struggle)」を理解する一助となるであろう。