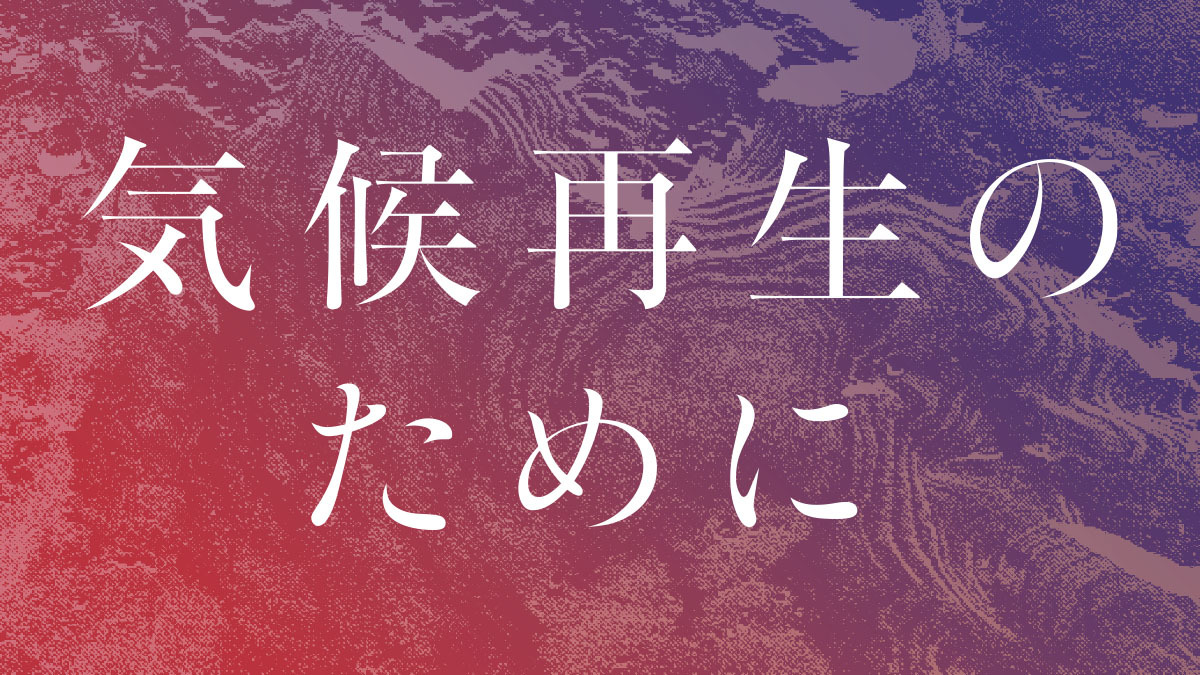「一・五℃」を超えても絶望しないために(江守正多)
※『世界』2025年11月号収録の記事を特別公開します。
実は今回が本連載で筆者が担当する最後の回です。これまで気候変動問題の科学と社会の諸側面について、筆者なりに論じる機会をいただいたことに感謝しています。
今回はそのまとめの意味も込めて、目前に迫る世界平均気温上昇「一・五℃」という現実を前に、私たちがそれをどのように受け止め、どのような姿勢で歩んでいけるのかを考えてみます。
日本の記録的猛暑と世界の温暖化
二〇二五年の日本の夏は驚異的な猛暑でした。日最高気温は観測史上最高を大幅に更新する四一・八℃を記録し、各地で熱中症搬送者が急増しました。多くの人が気候変動の深刻さを身近に感じたのではないでしょうか。筆者も講演や取材で、地球は後戻りできない「ティッピングポイント」を超えて加速段階に入ったのか、といった質問を何度も受けました。
しかし、世界平均気温を見ると、二〇二三年から二四年に大きく上昇した後、二五年は前年より落ち着いた水準で推移しています。つまり、今年の日本の夏の異常な高温は地球全体の温暖化の加速を直接示しているわけではありません。
この夏の日本の暑さは、太平洋高気圧とチベット高気圧が日本に張り出し、偏西風が北偏するという天候パターンが大きく影響しました。さらに日本周辺の海面水温の高さが重なりました。海面水温の上昇には太平洋十年規模振動といった自然変動も関わっていると考えられ、今後はある程度落ち着く可能性があります。
つまり、地球全体の温暖化は、今年の日本の夏のようなペースでは進んでいないので、少し安心してください。しかし同時にこのことは、現在の地球温暖化のレベルは、自然変動の出方次第で今年の日本の夏のような驚異的な高温が実現しうるほどには、「すでに高い」ということを意味しています。
「一・五℃」を超えることの意味
一方で、長期的な地球温暖化は確実に進行を続けています。現在、人間活動による世界平均気温の上昇はすでに産業革命前を基準に一・三六℃上昇と評価されています(自然変動の上振れを含めると一時的に一・五℃を超えています)。上昇速度から見て二〇三〇年前後にはこれが一・五℃を突破する見通しです。年間約四〇〇億トンの二酸化炭素排出を数年で急減させるのは現実的に不可能で、この見通しが大きく変わることはないでしょう。
ここで確認しておきたいのは、「一・五℃」という目標の意味です。この数字には、原因に責任が無いにもかかわらず深刻な被害を受ける脆弱な人々や将来世代を見捨てないという、国際社会の決意が込められていました。したがって、一・五℃の超過を受け入れることは、彼らに対して「ごめんなさい。あなたたちを救えませんでした」と告げることに等しいのです。
一・五℃を超えることで、氷床崩壊などのティッピングポイントを超える可能性も高くなります。そしてその被害を最初に、最も深刻な形で受けるのもやはり弱い立場の人々です。私たちはその事実を沈痛な思いで受け止めざるを得ません。
この状況を考えるとき、筆者はガザの現状を思い出します。飢えに苦しむ子どもの姿などを報道で目にするたび、受け入れがたい残酷さを感じます。しかし私たちは同時にその現実をある意味で受け入れてしまっているともいえます。無力感と罪悪感に苛まれながらも、人によっては署名などの小さな行動を積み重ねつつ、一刻も早い事態の改善を願うしかありません。
「一・五℃」を受け入れることも、それに似ているのだと思います。海面上昇や高潮や干ばつによって、世界各地で水や食料を失い、住処を追われる人々が現実に存在します。私たちはその人々に思いを馳せ、現実を受け入れつつも、「決して受け入れてはならない」と強く心に刻む必要があります。そして一刻も早い事態の改善のために、脱炭素化を加速させる努力を続けるしかないのです。
ポピュリズムの時代の気候政策
では世界が実際に脱炭素化へ進む見通しはどうでしょうか。ここで注目したいのは国際政治の大きな潮流です。慶應義塾大学の細谷雄一教授によれば、世界は「時代の転換点」を迎えています。冷戦終結からの三十数年は、民主主義やグローバリズムが拡大する楽観的な時代でした。しかし現在は大きな揺り戻しが起きており、これから数十年はナショナリズムとポピュリズムの時代になるとの指摘です。
もしこの見立てが正しいとすれば、気候変動対策は一層難しくなります。パリ協定は、世界の共通の脅威である気候変動に対して国際協調によって立ち向かうというビジョンへの合意でした。しかしナショナリストや右派ポピュリストはしばしば国際協調を拒み、科学的認識さえねじ曲げます。トランプ政権下の米国はその典型です。もし他の国々でも同様の勢力がさらに台頭すれば、国際協調の枠組みは脆弱化し、人類の希望はさらに遠のくでしょう。
その中で残されているようにみえる希望の一つは、ポピュリズム的な要素を持ちながら現実的な政策を進める「ポスト・ポピュリズム」と呼ばれる潮流です。その代表例がイタリアのメローニ政権で、移民には強硬ですが、営農型太陽光発電を進めるなど気候変動対策では実務的な一面を示しています。国益を重視する政権であっても、現実には脱炭素を避けられないと判断しうることを示しています。
米国の将来も重要です。次の大統領選挙の結果が国際協調の行方を大きく左右します。希望を託せるのは若い世代でしょう。共和党支持層の若者の中にも気候変動対策を支持する声が広がっていると聞きます。投票行動や草の根の活動を通じ、米国を再びパリ協定に引き戻す力になるかもしれません。未来を担う世代が、新しい方向を切り拓けるのかどうか。そこに私たちの希望があります。
エネルギーシステムの転換点
もう一つの希望は、技術と経済の側面にみえています。二〇二四年に世界で新たに導入された発電設備の容量のうち、九割以上を再生可能エネルギーが占めました。これは世界のエネルギーシステムが、すでに歴史的な転換点を超えたことを示しています。
太陽光や風力、そして蓄電池のコストは過去十年で劇的に下がりました。従来の火力発電よりも安価に電力を供給できる地域が広がり、しかも建設期間も短いため、途上国にとっても再エネは現実的な選択肢になっています。
米国ではバイデン政権の再エネ支援策がトランプ政権でほとんど止められますが、市場の流れを完全に止めることはできません。再エネはすでに競争力を持ち、企業や自治体レベルでは導入が進み続けています。
この流れを牽引しているのが中国です。国内で再エネと電気自動車を猛烈に普及させ、エネルギー需要が増え続けているにもかかわらず、二〇二四年から二酸化炭素排出量は減少に転じました。さらに安価な太陽光パネルや蓄電池を世界に供給し、アフリカなどでの普及を後押ししています。
もちろん、中国依存の高まりは経済安全保障上の懸念を呼びます。資源の確保や供給網の多様化は課題です。しかし、市場と技術が生み出す変化の力は、政治の対立を超えて確実に進んでいるのです。
国益と人権の共存
では、この状況で私たちは何を考えるべきでしょうか。一つ言えるのは、気候変動問題を「西側先進国のリベラル政権が世界を説得して進める」ような旧来の構図で考えることは、もはやできないだろうということです。これからは保守政権や新興国が主役となる場面も増えるでしょう。そのためには国益の追求として気候政策を位置づけるナラティブが重要な意味を持ちます。
日本についていえば、再生可能エネルギーの拡大は、化石燃料の輸入を減らすことで貿易収支を改善し、エネルギー自立性を高めます。営農型太陽光発電は農家の収入を安定させ、酷暑下の作業環境を改善し、食料安全保障につながります。国益の観点から見ても、脱炭素は合理的な道なのです。
同時に、国益だけで気候政策が進むとすれば不安もあります。その過程で様々な形で権利を侵害される人たちに目配りし、制度改善を求めることはリベラル勢力の重要な役割になるでしょう。国益のナラティブと人権のナラティブ、この二つを対立させるのではなく補完的に共存させることが、日本国内でも世界においても、立場の違いを超えて脱炭素化のビジョンを維持する戦略の一つになると思います。
「私たち」が無力でなくなるとき
最後に、筆者自身の立場について述べます。世界が本当に脱炭素化へ進むのかどうかは、正直なところ、運を天に任せているような気持ちです。そこに影響を及ぼす力を持っているかというと、自分一人ではほとんど無力です。
それでも、筆者は「脱炭素を進めたい側」に立って生きることを選びます。その選択が自分の人生に何らかの肯定的な意味を与えてくれるように思うからです。そして、同じ側に立つ人たちが増えることによって、「私たち」は無力ではなくなると信じています。
「一・五℃を超える」時代は避けられません。筆者は絶望せずにその時を迎え、そしてその先も、前へ進もうとする人々とともに歩んでいきたいと思います。