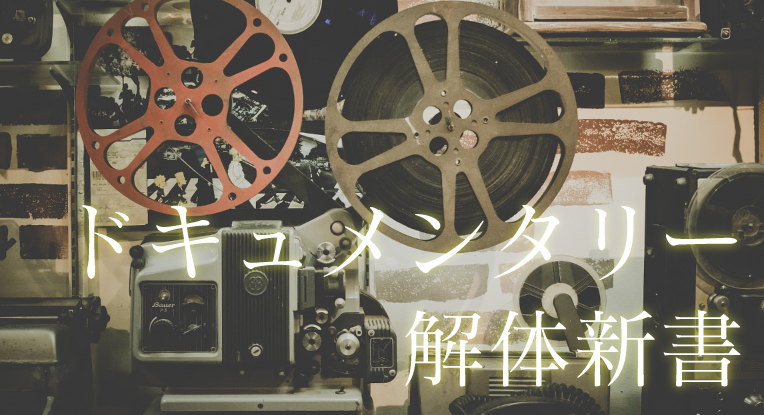沈黙を強いる力への抵抗 〜映画『太陽の塔』が問いかけるもの/石原大史
高度成長期の「裏」の顔
2011年、原発事故直後の福島で、私は被災者の取材に明け暮れていた。放射能汚染によって故郷を追い立てられた人々。その言葉を今も時々思い出す。
「もう一度災害があれば俺たちは忘れ去られる。それまでが勝負なんだ」。
それから7年が過ぎた。大規模の災害は「もう一度」どころか何度も起きた。この言葉通り、福島第一原発事故の経験は、おおかたの人々にとって、過去のことになってしまったのだろうか。一方、被災者が「勝負」を賭けたはずの「復興」は、思うような形で進んでいるとは思えない。文明の転換を叫んだ声も、いまでは耳を澄まさなければ聞こえなくなってしまった。
大阪千里丘陵・モノレールで万博記念公園に向かう。車窓から見えてきたのが、その像だった。岡本太郎作・太陽の塔。高さ70メートル、横幅25メートル、奇怪なデザインの巨像である。正面のよく知られたフォルムの裏側に、暗く冷たい表情をしたもう一つの顔がある。「黒い太陽」と呼ばれるこの顔は、近代科学の到達点である原子力を象徴しているそうだ。物言わず、ただ佇む太陽の塔。その顔は、悲しげにも見えれば、狂気を抱え、叫び声を上げるのを押し殺しているようにも見える。

太陽の塔背面の「黒い太陽」©2018映画『太陽の塔』製作委員会
残された太陽の塔、そして原発
私が子どもだった80年代、岡本は「芸術は爆発だ!」と絶叫しテレビで人気を博していた。現代芸術家だと言うが、当時は作品を見たことはなかった。いや、太陽の塔だけは知っていた。あの奇怪な塔を作った、変わったおじさん。それが当時のおおかたの岡本へのイメージであったのではなかろうか。
その頃、福島第一原発では6基体制が完成し、発電した膨大な電力を、東京圏へと送り続けてけていた。福島に暮らしていた私は、父親が見たがるニュースに、時折それが登場していたことを覚えている。しかし、ニュースの意味は理解できず、原発の空撮映像を退屈さの象徴のように感じていた。
私は何も知らなかった。そして知らされてもいなかった。
それから30年がたった。岡本は既にこの世を去り、太陽の塔は今も残っている。事故を起こした原発では、この先30年はかかるという廃炉作業が続いている。福島では避難指定地域の大半が解除され、人々の帰還が進められている。
岡本太郎は、登場しない
そんな時代に、まもなく封切られるのが映画『太陽の塔』である。監督は関根光才。これまでCMやミュージックビデオを中心に活動し、数多くの国際賞を受賞するなど、既に十分なキャリアを持つ。商業的な成功も、作家としての名声も手にした彼が、なぜ今、岡本太郎・太陽の塔なのか。そして、なぜドキュメンタリーなのか。
映画には、哲学者、文化人類学者、宗教者、批評家、芸術家など岡本太郎・太陽の塔に関わった、あるいはそこから何かを受け取った29名の人物が登場する。彼らは、時に嬉々とし、時に頭を抱えながら、岡本太郎・太陽の塔を語る。
科学技術がもたらす進歩を礼賛する時代への反逆、若くして留学したパリでの反ファシズム体験、縄文を中心とした日本文化の古層との出会い……。あのブラウン管の中にいた岡本からはうかがい知ることが出来なかった芸術論。その射程の広さと深さと同時に、現代を撃つ視覚の数々に驚かされる。
一方、29名もの人物たちが雄弁に語るのに対し、岡本太郎自身の肉声は、僅かに扱われるに過ぎない。岡本は生前に膨大な著作を残しているし、本人の肉声が記録された映像記録は大量にあったにも関わらず。ここに、本作を読み解く、もう一つの鍵があるのかもしれない。

岡本太郎 ©2018映画『太陽の塔』製作委員会
沈黙を強いる力への抵抗
この映画は、岡本太郎・太陽の塔「の」映画ではない。岡本太郎の伝記的事実の詳細や太陽の塔の制作秘話が主題であれば、「の」映画として紹介できよう。それらは本作でも扱われるが、映画の中心にはない。中心にあるのは、別な問い。我々は太陽の塔から何を受け継ぐことが出来るのかという関根の問いである。
つまり、これは、岡本太郎・太陽の塔「を巡る」映画なのだ。
本作の中盤、数少ない岡本の肉声に次のような言葉がある。
「芸術家と言うことがただの画家であることだとは思わないのです。全体的な普遍的な存在として生きるのです。世界の全てを知らなければならない」。
岡本はヨーロッパ体験を通して、全体主義を生み出した西洋文明の行き詰まりを肌身を持って感じていた。その岡本にとって芸術とは、一部の好事家を満足させる玩具を提供することでもとでも、大衆の興味を引く消費財を提供することでもない。彼にとって芸術とは、社会や文化の現在のあり方を問い直し、その刷新を促す行為なのだ。
この岡本の芸術家像は、関根のそれと近似系に見える。関根は2011年の東日本大震災・福島第一原発事故をきっかけに、映像作家らによる表現集団NOddINを結成、戦争と平和、原子力のあり方など、現代日本の課題を析出する映像作品を世に問い始めた。関根はNOddINの結成の際に、こんな文章を寄せている。
「初めて映像を志した時 よりよい世界を作れるようなもの それが作りたいと思った。いまがその時だ」。
この芸術家像を共有する岡本・関根が、日本社会との緊張を内包していると想像することは容易である。「芸術家が政治を語るな」。「仕事を干されるぞ」。社会を題材にした表現には、雨後の竹の子のように批判が巻き起こる。「おまえたちは玩具を作っていれば良いのだ」と。この映画は、そうした沈黙を強いる力への抵抗なのだ。

ビキニ水爆実験をモチーフにした「明日の神話」©2018映画『太陽の塔』製作委員会
「を巡る」という接近
本作の終盤、映画は岡本太郎・太陽の塔、そのものから飛翔していく。登場人物たちは、福島第一原発事故のもたらしたインパクト、その後の日本社会の閉塞を口々に語っていく。もちろん岡本は福島第一原発事故を経験していないし、原子力発電そのものについての岡本自身の肉声が紹介されるわけでもない。ただ、原子力を象徴しているといわれる「黒い太陽」という接点があるのみである。
お行儀の良い岡本太郎・太陽の塔「の」ドキュメンタリーであれば割愛を余儀なくされたテーマかもしれない。しかし、これは「を巡る」映画なのである。
文明の刷新を訴え、全世界を背負う気概を芸術家の使命とした岡本の思想、芸術観を内在的に理解しようという映画の試みは、現代社会のこの問題に行き着かざるを得ない。
それが岡本太郎・太陽の塔のメッセージを受け取った関根の意思なのだ。
映画を見た者は、全編にわたる言葉の速射砲を浴び、劇場を出ることになるだろう。
我々は知ってしまった。知らないとはもう言えない。そして考え込むのだ。芸術とは、文明とは、人生とは…。太陽の塔は、「私」に何を問うているのだろうと。
『太陽の塔』 (2018年/日本/112分)
監督:関根光才/撮影:上野千蔵/照明:西田まさちお/録音:清水天務仁/編集:本田吉孝/本編集:木村仁/音響効果:笠松広司/音楽:JEMAPUR/製作:映画『太陽の塔』製作委員会/企画:パルコ/製作:スプーン

公式HP
9月29日(土)より 渋谷シネクイント、新宿シネマカリテ ほか全国順次公開
配給:パルコ