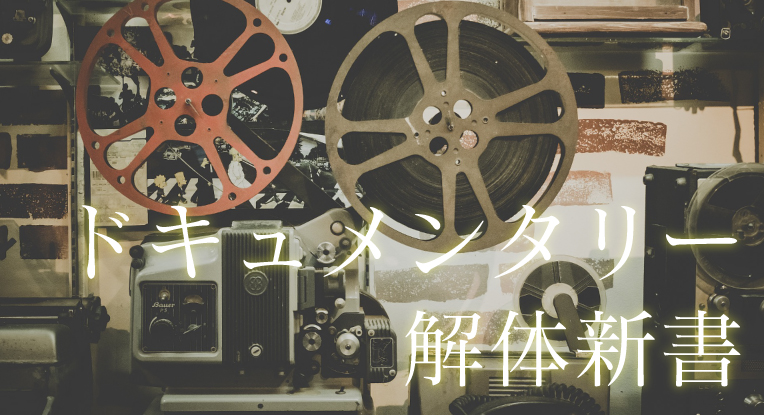自死は、向き合える〜『牧師といのちの崖』が映し出す自死未遂者と支援者の物語/杉山春
 ©ドキュメンタリージャパン、加瀬澤充
©ドキュメンタリージャパン、加瀬澤充 カメラが一人ひとりの表情をしっかりと捉えている。自死未遂者の表情も、支援する側の牧師の表情も。だから、一人ひとりが何を感じているか、ごく自然に伝わってくる。
和歌山県白浜町の三段壁は、2キロに渡り高さ50メートルの断崖絶壁が続く景勝地であり、自死の名所でもある。その地で自死未遂者たちを支援する、藤藪庸一氏は白浜バプテスト基督教会の牧師だ。三段壁に設置されたいのちの電話の看板を見て電話をしてくる人たちを車で迎えに行き、必要な人には共同生活の場を提供し、さらに自立支援のため、弁当の店を開いて、一緒に働く。警察をはじめ地域の病院などとも連携している。
この活動は、これまで九百人もの人たちを助けてきたという。
ぎりぎりのところを乗り越えて、再び生に向き合う
私は2017年に『自死は、向き合える』(岩波ブックレット)を書いた。その過程で知ったことは、覚悟を決めた上での自死はほとんどないということだった。自死企図をする人たちは、直前まで迷っている。追い詰められ、ほかに選択肢はないという視野狭窄を起こしている。大半が、その時、精神疾患に近い精神状態にまで追い詰められているのだ。
だから、藤藪氏に電話をしてくる人たちは、極限の緊張の中で、生きる理由を探している。離婚して、リーマンショック後の経済不況の中で、仕事も失った男性は、コンビニ強盗をしそうなほど追い詰められて、4年前、ここまできた。カメラの前でその話をしている時には、時折硬い表情を見せるが、自立支援の活動のリーダー役を頼まれ、スタッフとして働くうちに力強い表情に変わっていく。
料理の仕事のなかに、面白みを見出したという男性は、自然な表情で人に美味しいと言ってもらう楽しみを語る。そして、「こんなことを自分が言うとは思わなかった」と死に追い詰められていた当時を振り返る。
だれからも必要とされていないと確信したときに、自死企図をしたと語る青年は、洗礼を受けたあと、とびきりの笑顔を見せた。
ぎりぎりのところを生き延びて、生きる理由を見つけた人たちは、当たり前の表情を取り戻していく。藤藪氏の活動の力だ。

藤䉤庸一牧師(©ドキュメンタリージャパン、加瀬澤充)
決して「ドラマチック」ではない、生きのびた後の物語
もっとも、ノンフィクションの面白さは、物語が順調には進まないところだ。自死まで追い詰められた人たちは、生きることへの恐怖や社会への深い不信の中にあえいでいる。その痛みが深ければ深いほど、支援者の思惑は手酷く裏切られる。その葛藤を加瀬澤充監督は、しっかりと描き撮っていくのだ。
三段壁から電話をしてきた女性は、数日後、こんなところ、二度と来るものかという勢いで藤䉤氏を振り払うように、宿舎を後にする。
自立支援として食堂で働いてお金を貯めた男性は、そのお金を親に送金して、過去を清算し、対人関係を改善しようと藤藪氏に迫られて、顔を歪めて憮然とする。
終始硬い表情の青年は、カメラの前で仕事先での使命感を語った直後に、実は収入以上にお金を使っていることを藤䉤氏に指摘される。貯金通帳のお金を全部下ろしてくるようにと厳命されてしまう。さらに、仕事先で人間関係のトラブルが起きる。藤䉤氏に、いくら注意をされても、その人間関係を解決しようとしないのは「悪意がある」とさえ言われる。その厳しい言葉に、唖然とする青年。正直、見ていて青年が気の毒になる。
カメラは恐れることなく、支援に乗り切れない人たちの心の内を描く。
この青年はサービス精神が旺盛で、監督を案内して、死にたいと思って座り込んでいた三段壁の淵にまで出かけていく。そして、その時のことを精一杯語ろうとする。「寂しくて、寂しくて、誰にも何も言えないまま、死んでいってもいいのかなと思った。その時、花火が上がるのを見た」と。だが、そう語る彼の表情は無表情だ。監督の願いに精一杯応えようとする彼の不安も垣間見える。
藤䉤氏の活動は、妻の亜由美さんによって支えられている。亜由美さんは苛立つ夫に、共同生活者の面倒臭い言葉が聞けなくなっていないかと明るく指摘する。
彼女は以前の自殺企図者と現在の企図者の違いを明確に説明する。かつては親がいないために孤立して、死を選ぶ人たちがいた。今は、親がいて、連絡を取っていても、親に頼れない若者が死を選ぶという。今や、家族という仕組みが、人を支え切れなくなっているのだ。その上で「皆の実家になればいい、何度でも戻って、立て直していける場になればいい」と亜由美さんは覚悟を語るのだ。
40歳手前の人たちが自死をしにくるという。時代が生み出した人生に限界を感じた者たちを、人としての限界を抱えた藤䉤氏が悪戦苦闘して支えようとしているのだ。
もう一つ、藤䉤氏を支えているのが祈りだ。教会の集まりの中で、率直に自分の弱さを語り、「神の国を見せてください」と願い、「キリストに従っていく」と決意を示す。また、「正しい答えはない」と言い、「最も苦しむ人の心は神にしかわからない。そこは神に委ねて、救いの希望を語りたい」と言う。
自死支援の現場は決してドラマチックではない。企図者の苦しみは、思い通りに支援が進まない牧師の苦しみだ。

崖の先端に設置してある「いのちの電話」の連絡先(©ドキュメンタリージャパン、加瀬澤充)
自死の問題と向き合う
日本の社会は自死を語ることを好まない。だが、死因としては7〜8番目。ありふれた死だ。交通事故死は年間、3500人強。その6〜7倍が自死で亡くなっている。
2014年に世界保健機構(WHO)が出した自殺レポート『自殺を予防する 世界の優先課題』(Preventing Suicide : a global imperative 独立行政法人国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所自殺予防総合対策センター訳)で、前WHO事務局長のマーガレット・チャン氏は「自殺とその予防についての研究や知識が増えているのにもかかわらず、自殺にまつわるタブーとスティグマは根強く、人々は援助を求めることなく、しばしば取り残されています。しかし自殺は予防できます。(中略)適時かつ効果的な科学的根拠に基づいた介入、治療と支援により、自殺と自殺企図は予防できるのです」と語っている。自死を防ぐ社会制度・支援制度の構築や治療法の確立は、さらに進展させられ得る分野だ。だが日本社会で、自死に対する表現は稀だ。だから、論理的な対策が十分に進んでいるとはいえない。
自死はもっと語られる必要がある。なぜなら、企図者たちの多くが、時代の変動のなかで翻弄され、苦しみを背負った当たり前の人たちだからだ。支援者もスーパーマンではない欠点を持つ一人の人だ。ただし藤䉤氏には周囲に支える人がいる。さらに、祈ること、委ねることを知る人だ。
私たちの社会では今、そのようにして、時代の裂け目が繕われている。
2018年|100分|カラー|英題:A Step Forward
監督・撮影・編集:加瀬澤充 / プロデューサー:煙草谷有希子 /音響:菊池信之 /音響助手:近藤崇生 /宣伝協力/細谷隆広 /宣伝デザイン:成瀬慧
出演:藤藪庸一
製作・配給・宣伝:ドキュメンタリージャパン、加瀬澤充
公式HP 「牧師といのちの崖」
1月19日よりポレポレ東中野で公開中