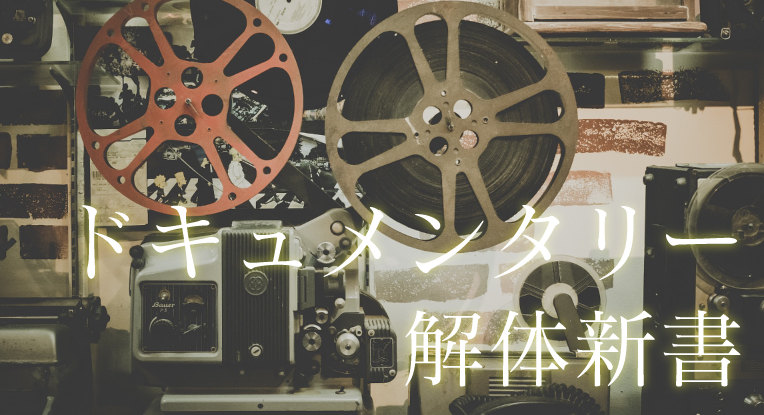塀の中の少女たちが気づかせてくれること —— 「少女は夜明けに夢を見る」/坂上香
指紋をとられる少女
重いテーマの映画は、敬遠される。この映画も、罪を犯した少女たちが主人公で、彼女らを取り巻く現実は、貧困、虐待、DV、薬物、性暴力…と過酷で、悲しく、理不尽なことばかり。にもかかわらず、「観たほうがいいよ」と人に伝えたくなる映画だ。
舞台は、イランの少女更生施設。入所手続きとして、一人の少女が指紋を取られるシーンから始まる。ぷっくりした白くて可愛らしい指。その指が、黒いインク板に押さえつけられ、順々に指紋が取られていく。大人の指に包みこまれ、強制的に用紙に押し付けられながら。
そこにはさみこまれる、ヒジャブをまとった、はかなげな少女ハーテレの顔。ほんの一瞬、微細に歪む表情が、印象に残る。そして、洗おうとしても、なかなか落ちないインク。よく見ると、ハーテレの手は火傷と自傷の痕だらけだ。
なんと象徴的なイントロだろう。「非行少女」という社会的烙印を押されていくプロセスや、その影に隠された少女の素顔が、指紋押捺の一連に、凝縮されている。
極め付けは、タイトル前のクレジット。メヘルダード・オスコウイ監督の名前に、指紋(おそらく監督自身のもの)が重なるのだが、少女たちへの連帯が感じられ、胸に熱いものがこみあげてきたのだった。
劇映画のようなドキュメンタリー

冒頭から劇映画的なトーンで、リアルというよりは絵画的だ。イランを代表する映画監督アッバス・キアロスタミにしても、彼の愛弟子のジャファル・パナヒ監督にしても、ノンフィクションとフィクションを掛け合わせた独特の作風だから、実はこの映画も、彼らのように素人の俳優を採用した劇映画かと思いながら見始めた。
しかし、途中から、むしろオーソドックスなドキュメンタリーの手法であることに気づかされた。少女たちのふるまいや表情の機微は、脚本に従って再現できるものではない。むしろ、撮れるはずがないものが撮れていることで、フィクションの印象が生まれたのではなかったか。
冒頭の指紋押捺の場面一つとっても、通常は、施設側が取材者を入れること自体、考えられない。未成年の少女たちが、顔をさらして、率直に、犯した罪や被害について語っているのも驚きだ。皆が寝静まった頃、出所間際の少女「名なし(シャガイエ)」に、監督がひそひそ声で話しかける場面がある。それは、夜明け前に、撮影クルーが更生施設にいたことを意味する。
本作品では、こうしたありえない場面が撮れている。しかも、ふんだんに。
なぜ女の罪は男より重いの?

少女たちが、一人の人間として多面的に、イキイキと描かれていることも、劇映画と見まごう理由の一つだったかもしれない。
雪合戦やゲームをして幼女のようにはしゃいだり、撮影のマイクをつかんで一人が歌い出したかと思えばミュージカルさながらのコーラスに発展したり、大粒の涙を流しながら電話の向こうの親族に「見捨てるのか」と文句を言ったり、インタビューごっこや人形劇で悲惨な生い立ちや罪を笑い飛ばしたり。
少女たちの知性にも驚かされる。たとえば監督が「ここは“痛み”だらけだね」と語りかけると、父親を殺したソマイエは、能面のような表情で答える。
「四方の壁から染み出るほどよ。もうこれ以上の苦痛は入りきらない。」
思わず、映像を一時停止したくなるほど、心が震えた。ソマイエの詩的・文学的感性は、トラウマと癒しをめぐる詩集『ミルクとはちみつ』の著者ルピ・クーア並である。だからこそ、こうした宝石のような表現の余韻を、もっと味わいた
少女たちは、したたかさで賢い。裁判から帰ってきた少女が、裁判長に見せた「反省のふり」を皆に面白おかしく報告する場面は、ダルク(薬物依存症者の回復施設)の女性たちからもよく聞く「あるある話」だ。
また、施設を定期的に訪れるイスラム法学者が「人権について話そう」と切り出す場面があるが、待ってましたとばかりに少女らから声があがる。
「女より男を殺したほうが、なぜ賠償金が高いの?」「女は共犯者も罰せられるのに、男はそうじゃないです。なぜですか?」「父親は子を殺しても罰せられない。子の命は父親のものなの?」「神様が女性だと思う人はいませんよね?」
いずれの問いも鋭く、まっとうである。それに対する法学者の反応は、全くの肩透かしで、返答になっていない。嘘臭い現実を生きなくてはならないのはいずこも同じだが、女性へ
矯正施設を撮影することの困難さ
私にとって、これは、自由と制約を問う映画でもある。
今春、私は日本の刑務所を初めて舞台にした映画『プリズン・サークル』(2020年1月公開予定)を完成したばかり。国や制度は違えど、取材許可や撮影の困難さは私も経験してきた。
撮影の許可が降りるまでにオスコウイ監督は7年、私の場合は6年かかった。いずれも保守的な国の機関であるから、撮影に関する制約は厳しいはずだ。
しかし、イランでは企画が通る前にパイロット版の制作が許されていたり、施設職員が撮影に協力的だったり、被写体との個別対応が許されていたり、出所日の事前告知があったり、と資料を読むだけでも、日本の撮影条件とは、天と地の差だったことがわかる。
そもそもイランの更生施設には、自由に会話ができたり、歌ったりできる環境がある。一方、日本の矯正施設に、そんな環境はない。声を荒げたり、決められた所作以外の動きをするだけで、懲罰の対象になる。
オスコウイ監督が、被写体と信頼関係を築ける環境にあったことも、少女らの表情やふるまいを見れば一目瞭然である。例えば、ある少女は監督に同じ年の娘がいることをすでに知っている。そして、ゴミの中で育った自分の境遇との違いにフェアじゃないと涙ぐむ。別の場面では、少女たちが我も我もと、監督が大学の先生であり、大学で見せるために映画を撮っていると口にする。
日本の矯正施設は、ドキュメンタリーに不可欠な信頼関係を育むこと自体を禁じているから、このような展開はあり得ない。映画の撮影時、私たちは一切の会話や接触、挨拶や目を合わせることすら禁止されていたのである。
決定的な違いのもう一つは、少女たちが顔出しをしている点。監督が被写体本人たちから直接許諾を得たのだという。一方、日本の法務省は、矯正施設の収容者に対して、年齢に関係なく、全て顔出し不可。「受刑者の人権に配慮して」がその答えである。
人権に本当に配慮するなら、個別に対応すべきである。私はこの件で、法務省とギリギリまで交渉を続けてきた。しかし、10年かかっても覆せなかった。顔を隠すことで、伝えられなかったことがあまりに多過ぎる。言い換えると、観客側も知り、学ぶ機会を奪われたのである。私たちはもっと要求していい。少女たちの表情は、そのことを改めて問うてくる。

不寛容な社会で見る夢は
映画を見ながら思ったのは、この国の不寛容な人たちのことだった。
当たり前だが、少女たちにはそれぞれ、罪を犯すに至った背景がある。個性や感情を持った一人の人間である。しかし、そうした当たり前なことが、この社会では、ますます共有されにくくなっている。
「犯罪者が笑ったり、楽しんだりするのは許せない」「人を殺したら殺されて当然」「人を殺したヤツらと同じ空気を吸いたくない」「更生のために税金を使って欲しくない」「被害者にも落ち度がある」
こうした辛辣な声は、ネット空間に留まらず、非常勤先の大学であったり、マスコミ関係者だったり、足元からも聞こえてくる。彼らは、自分と暴力の間にきっちり境界線を引く、〈共感を抱けない〉人たちである。
しかし、電車では、隣に少年院戻りの少女が座っているかもしれない。コンビニの列に並んでいるのは、家で子どもを虐待している人かもしれないし、DVから逃げている最中の人かもしれない。ひょっとすると、〈共感を抱けない〉人自身が、いじめを苦に、自殺を考えたことがあったかもしれない。逆に、誰かをとことん追い詰めたかもしれない。加害、被害はあちこちに存在する。
彼らが、スクリーンを通して、少女たちに出会う姿を想像してみる。
父親のDVから母を助けるために「父を殺すことはみんなで決めた」と真顔で言うソマイエ、監督から夢は何かと聞かれ、うつむきがちに「死ぬこと」と笑顔を見せるハーテレ、12歳でおじから性的虐待を受け「簡単には人は殺せない。おじならいいかも」としれっと言う「名なし」。
シャバに絶望させられてきた少女たちは、高い塀に囲われた施設のなかで、相手に耳を傾け、苦しみをぶちまけ、語れない子にはベッドの脇に座って涙をぬぐい、ハグをする。
そんな〈共感する〉少女たちに、〈共感を抱けない〉人たちは、何を見るのだろう。
『少女は夜明けに夢を見る』/原題 Royahaye Dame Sobh /英題 Starless Dreams