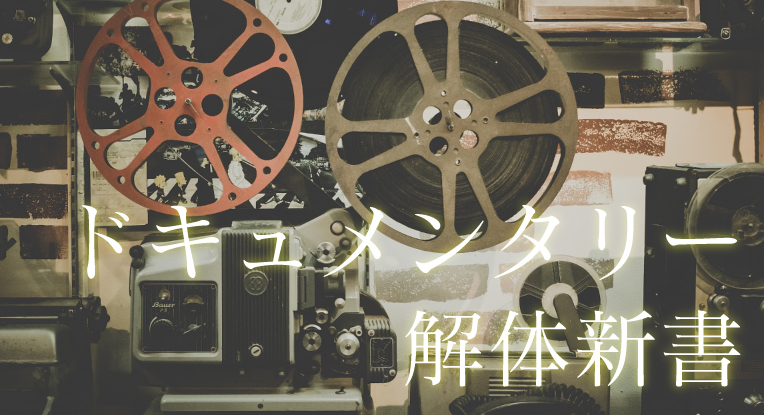「家で死ぬ」ことのリアル—『人生をしまう時間』/宮子あずさ
『人生をしまう時間』は、NHKBS1スペシャルで放送されたドキュメンタリー『在宅死“ 死に際の医療”200日の記録』に、シーンを追加・再編集して映画化した作品。医師の小堀鴎一郎氏を中心とした訪問診療のチームが「家で死にたい」と望む9人の患者の家を訪れた、まさに生きた記録である。
小堀氏は80歳。長く外科医を務め、定年後高齢者を対象とした訪問診療に転じた。拒絶的な患者に対し、気持ちを察しながらも、必要なことははっきり伝える。毅然とした口調の一方で、老いを分かちあう暖かさを共有しているようも見える。
住環境のリアル
私がこの作品に引きつけられたのは、まず患者が暮らす住環境が、ありのまま、リアルに描かれていたことだった。例えば、93歳の男性の家では、ベッドのすぐ横に電子レンジやテーブルがあり、起きて一歩踏み出せば手が届く。電子レンジを操作するのに、邪魔だったのだろうか。テーブルに直に置かれた食べかけのサンドイッチがひどくリアルで、苦しくなった。
私自身は精神科病院の訪問看護室に勤務し、似たような光景をよく見ている。老いや病によって生きる余力が奪われた人は暮らしは、雑然としがちである。それはごく単純に言えば、不衛生で、ものがぐしゃぐしゃになった状態にほかならない。具合が悪い状態で家で過ごせば、多くの場合、最終的には食と排泄の場が極めて接近する。
在宅医療に携わる者は、こうした環境に臆せず入り、普通にそこに落ち着いておしゃべりをする。そうしたある種の鈍感さが求められるのが、私にとっての在宅医療の現場である。
恐らくはかなり汚れている布団に触れ、患者を抱えて起こす。それを当たり前のこととして行う医師や看護師は、観客として見ると、その無頓着さもプロならではの所作に見えた。患者と医療者双方のリアルなありようが、作品からひしひしと感じられる。

「死ぬときに誰がいるか」ではない
作品で描かれる死は、実はさまざまである。「帰りたい、どんなボロいうちでもね」と帰宅を果たし、家族に看取られた人。家族の負担も考慮し施設に移った人は、その後がんになり、病院で最期を迎えた。また、ひとり暮らしで誰にも看取られない可能性があった人もいる。
長年ケアマネを務め、登場する患者の1人と長く関わった79歳のケアマネは、「本人が住み慣れたところに居たいというのは尊重してあげる。息を引き取る時は誰かが立ち会わなくても、それまでに深い関わりを持っていればいい。過程が大切だと思います」と語る。
私も、これには心から同意できる。病院でさえ、息が止まるその時に、誰かが居るとは限らない。家族全員で、息を引き取るところに居合わせなければいけない、と考えては、ゴールが高すぎ、そうできなかった時のダメージが、とても心配になる。その瞬間まわりに誰がいるかよりも、息絶えるその時まで、どのような関係を築いたのか。これこそが、大切なのである。
登場する9人のうち、8人は80代以上。その中でただ1人、50代の女性がいる。その人が婦人科系のがんを患い、強い痛みに苦しんでいる。世話をしている母親は70代。訪問診療によって麻薬を使っての症状コントロールが見事にはかられ、穏やかな日々が続いた。
その後やってきた死を、母親は穏やかに受けとめているように見えた。死という結末は変わらなくとも、そこに至る時間が穏やかであれば、見送る側の後味はまるで違うものになる。そうした母親の変化も、映像ははっきりと写し取っていた。
 盲目の娘は、自分をこよなく愛し育ててくれた父を日常の中で看取った
盲目の娘は、自分をこよなく愛し育ててくれた父を日常の中で看取った
今後、「在宅死」はよりいっそう身近に
ここからはとても現実的な話になる。今国の社会保障は、「ときどき入院、ほぼ在宅」の方針に貫かれている。入院病床は減らされ、入院の適応がかなり絞られている。入院によって画期的によくなる人以外は、入院できないと考えた方がよい。つまり、望むと望まぬとに関わらず、私たちはこれから、選ぶ余地なく、家で死ぬのが一般的になるだろう。
こうした政策には問題を感じつつ、死ぬまで家にいられるなら、それは悪くないとも思う。私の場合、一番の理由は死ぬまで猫と暮らしたいからなのだが。多少不衛生でも、薄汚くても、自分が大事にしているものを大事にしながら、最期までいければと思う。
そして、きっと、それは可能なのだ。訪問診療、訪問看護。居宅支援さえ充実していれば。だからこそ、そこが切り捨てられないかは、きちんと見ていこう。